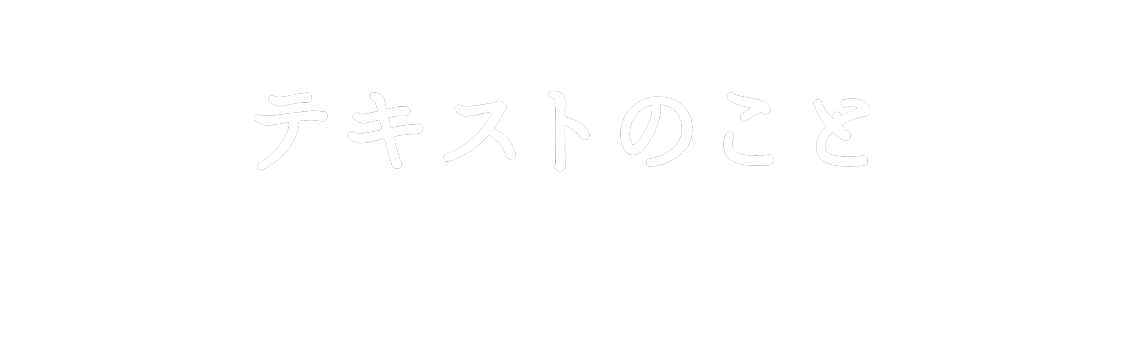本作の「テキスト」として、舞台上で発せられる台詞、劇中で歌われる歌詞、「音声ガイド(ストーリーテリング)」の執筆を担当した作家がどのように言葉を紡ぎ、創作を進めていったのかを紹介します。
目次
「月」と「息」から
はじまる、詩としての台詞
本公演の「テキスト」を担当する劇作家・演出家の三浦直之。依頼にあたって本作・演出の森山開次から渡されたのは、「主人公の詩人が"詩"を探すその詩を書いてほしい」という大きな方向性と、絵本のようなかたちで示された全体のストーリーラインでした。
蒸気機関車の絵とともに、構想段階から「月」というモチーフが強く存在していたといいます。森山との対話を重ねるなかで、「月」と並ぶもうひとつの大きな軸として浮かび上がってきたのが「息」でした。聞こえない人、見えない人など多様な方の観劇も想定される公演で、「息」をすることは、誰もが自身に持っている感覚です。「月」と「息」というモチーフの言葉遊びからテキストづくりが広がっていきました。
この作品では、旅を通して見つけた風景や音をレンが詩で表現します。舞台上に本物の夜空がなくても、レンの言葉によって観客の中に景色を立ち上げていきます。
あえて語らない言葉
「作品の中に、観客の想像の余地を残したい」という一貫した演出において、言葉はとても強い情報です。たとえば、舞台上にただ丸いものが浮かんでいるとき、観客の中にはそれを「月」と捉える人もいれば「太陽」と捉える人もいるかもしれません。しかしそこで役者が「月」と口にした瞬間に、その丸は「月」に確定してしまうのです。
だからこそ今回のテキストは、言葉が観客の想像を「固定してしまう」方向に働きすぎないよう、細心の注意を払ったと三浦は語ります。レンの過去や負っている傷、内面を直接語れば、物語としてはわかりやすい。しかし、人物像を限定せず観客ひとりひとりが自分自身の記憶や感情を重ね合わせられる余白を残すため、レン自身が自分語りをするテキストは意図的に避けられました。
レンの詩から観客それぞれの物語が立ち上がるようにすること――それが、この作品における「テキスト」の大きな役割になっています。
言葉を通して、
言葉に向き合い直す
劇作家として言葉を紡いできた三浦にとってもこの作品に関わることは特別な経験で、自身の中に「言葉に向き合う態度そのもの」の変化を感じたといいます。これまで何気なく使ってきた「見る」「聞く」といった表現さえ、一度立ち止まって考え直しました。「見る」とは何か。「聞く」とはどういうことか。「月」とは何か。「息」とは何か。そして、視覚や聴覚のあり方が多様な観客が集う場において、それらの単語がどのように受け取られるか。作品で使う言葉ひとつひとつを、精査していく作業が続きました。
一語一語に向き合う時間は、「言葉を通して、もう一度言葉に向き合い直す」経験をもたらしました。
ふたつのコトバの詩
本作の大きな特徴のひとつに、コトバが「音声」と「手話」の両方で表現されることが挙げられます。ろう者のドラマトゥルクとしてチームに参加するSasa-Marieの監修のもと、レンの詩を視覚的に表現するための試行錯誤が繰り返されました。
たとえば「錆びた寂しさ 吸い込んで」というフレーズ。Sasa-Marieは「寂しい」という手話を使うのではなく、涙の手話を行ってから、ふわっと残像のような余韻をつくる手話を挟み、その後に吸い込む動きを提案しました。三浦のテキストへの挑戦と同じように、手話という言語をどう芸術表現に昇華させるかというプロセスは、日本語を言語としての手話に置き換える作業とはまったく異なります。三浦のテキストを出発点にレンが日本語の詩で表現しているものを、同時に手話の芸術的表現によって伝える。テキストがもつ魅力と、手話が持つ魅力を融合させ、それらが効果的に響き合うポイントを探る日々が続きました。
レンを演じる岡山天音が声の台詞で表現するのに対して、手話と身体で表現することを担ったのが、ろう者でスチームダンサーの梶本瑞希です。レンの台詞の通訳という役割ではなく、音声と手話が対等に、2本のレールのように並走することを目指しました。その表現の構造自体が、本作の大きなチャレンジでもあるのです。
言葉が出すぎない歌詞
劇中では、歌詞のついた歌が3曲登場します。歌詞においても、「言葉が作品の中で上位に来ないこと」「歌詞が主張しすぎないもの」をとことん意識して言葉が紡がれました。
蓮沼しゅうた執太の音楽と、坂本美雨の声が重なった瞬間、「言葉が前に出すぎず、音や空間の中に溶けていく感覚があった」と三浦はいいます。自身が狙った、言葉が前に出すぎない状態を、音楽と声が体現してくれたのです。
『回る軌跡』歌詞
回る 回る 回る 回る 回る 回る
朝は夜に焦がれて闇に
夜は朝に憧れて羽に
回る 回る 回る 回る 回る 回る
回る 回る 回る 回る 回る 回る
(回る 回る 回る 回る 回る 回る)
朝と夜はほつれて雨に
夜が朝を連れて瞬き
『もののねの泉』歌詞
わすれ られた いつか いのり
わたし あなた あわい うたまい
(繰り返す)
『交響曲 月 最終楽章』歌詞
となり かなた ひかり こなた
てのひらから あふれたうた
みちびかれた さきにあなた
となり かなた ひかり こなた

音声ガイドという、
もうひとつのテキスト
本作の「テキスト」におけるもうひとつの試みが、「音声ガイド(ストーリーテリング)」も三浦が書き下ろした点です。抽象度の高い舞台上での表現に対して、音声ガイドはより具体的な言葉の選択をしています。舞台で起こることの説明ではなく、絵本の読み聞かせのようなものを目指して執筆が進められました。今回「音声ガイド(ストーリーテリング)」となっているのはそのためです。見える、見えないに関係なく、舞台上の音情報と重ねながら耳から物語を楽しめる鑑賞スタイルを追究しました。また、ご自身のスマートフォンにダウンロードして、どのお座席からも楽しめるガイドは、抽象度の高いダンス作品を見慣れていない人にとっても、気軽に使える鑑賞サポートとなります。全盲の俳優・関場理生(せきばりお)とバイオリニスト白井崇陽(しらいたかあき)がアドバイザーとなり、想像と理解のバランスを話し合いながらつくっていきました。ナレーションは、本作のスウィングキャストとして稽古場での創作に参加してきた田村桃子(たむらももこ)が担当し、稽古場で育まれた作品とカンパニーの空気感も感じられるものになりました。
本作のテキストの見どころ
「テキストについてもですが、これだけ多くの表現要素が同時に存在する舞台作品は、本当に珍しいと思います。たくさんの要素とキャストやスタッフの力がどう響き合っているのかを、あらゆる角度から感じてほしい」と三浦は語ります。
身体表現、音楽、歌、詩的なテキスト、手話、音声ガイド。多層的な表現が交差する中で、言葉の模索が続けられてきました。物語の解釈を押しつけるのではなく、舞台と観客をつなぐために必要な言葉だけを選ぶこと。その積み重ねが、観客それぞれに異なる景色を立ち上げる余白を生み出し、選び抜いた一語一語への誠実さこそが、本作のテキストの魅力であり、舞台を支える静かな力になっています。
音声ガイド(ストーリーテリング)使用方法
三浦直之が執筆した「音声ガイド(ストーリーテリング)」は、お客様ご自身のスマートフォン等の端末に配信するシステム「EG-G」にて提供いたします。専用アプリ「EG-G」を事前にインストールの上、公演コンテンツのダウンロードが必要です。ご利用の方は余裕を持ってご準備ください。ご利用の際はイヤホンの装着をお願いします。
※「音声ガイド」と「字幕」は11月28日以降にご利用いただけます。
・専用アプリ「EG-G」の使い方・専用アプリ「EG-G」ダウンロード(Google Play)・専用アプリ「EG-G」ダウンロード(App Store)