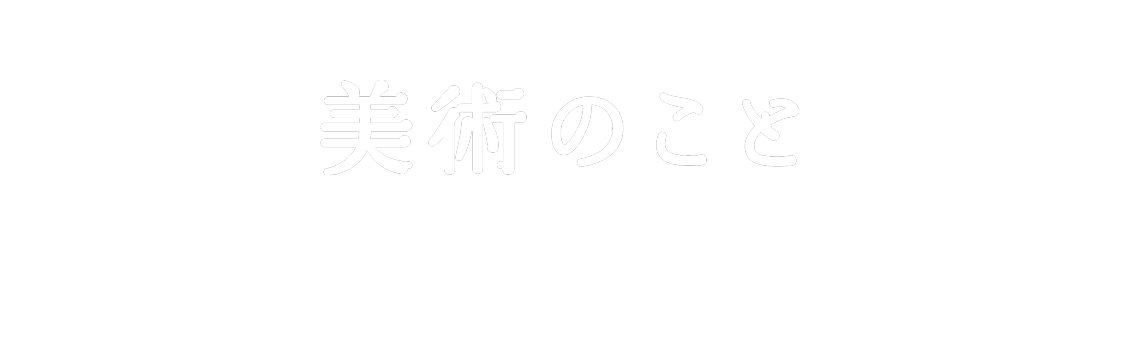ここでは、さまざまな個性や特技、身体的特徴のあるキャストが出演する本作の舞台美術が、どのようにアクセシビリティに配慮し、空間を形づくっていったのかを紹介します。
目次
舞台の前提を見直した
空間構成
袖幕
劇場では通常、「袖幕(そでまく)」と呼ばれる黒い幕が舞台の両脇に吊られ、「袖中(そでなか)」という舞台の裏側にいる出演者や道具が客席から見えないようになっています。しかし、この袖幕が出入りのスペースを狭めたり、車椅子がひっかかったりと、物理的な障害にもなります。
本公演ではその袖幕を取り払い、「舞台の前提」を見直すところから舞台美術の構想が始まりました。それに合わせて照明器具などを隠すために舞台上部に渡される「一文字幕(いちもんじまく)」も減らし、普段は隠される劇場の構造も美術の一部として空間に取り入れる工夫をしました。
袖中待合室
袖幕をなくすことで、新たな課題も生まれました。舞台裏への移動距離が長くなり、移動に負担を抱えるキャストもいるためです。そこで設けられたのが「袖中待合室」です。通常は袖の内側や楽屋にある待機場所を、今回は観客の視界にも入る上手と下手に約3×4mのコの字型の囲いを配置。完全には隠されることなく、舞台の風景の一部として存在します。
動き、呼吸する舞台装置
三角の月のステージとスロープ
本作の象徴的な装置の一つとして、高さ60cmの「三角の月のステージ」が登場します。車椅子のままアクセスできるよう、実地検証を経て傾斜を10度にしたスロープと接続することができる、三角形の台です。1辺は約4mで、舞台装置の中でも大きな構造体です。
三角形には、頂点へ向かう"矢印"のような方向性や、スピード感があります。ゴールドに塗られたそのステージは、まるで"三角の月"が光を放つように、物語の中心で観客の視線と想像を導きます。
カラクリワゴンとオルガンワゴン
舞台上手と下手にそれぞれ1台ずつ、車輪のついた2台のワゴンが配置されています。上手の「カラクリワゴン」は歯車やパイプが組み合わされたエンジンルームのような構造、下手の「オルガンワゴン」には足踏みオルガンが組み込まれ、パイプが連なる姿はパイプオルガンにも機械装置にも見えます。
これらはキャストによって動かされ、舞台の空間を変化させる"可動する美術"です。どちらも実際に音を出すことができ、動き、呼吸する――そんな生命感を持った装置として、舞台と音楽をつなぎます。

想像力で変化する小道具
客車ベンチとSLトランク
SL機関車を舞台に物語が展開する本作では、2種類のSL車両が制作されました。大きい方の「客車ベンチ」(約90×40×45cm)は、SLムジカの和合由依が乗る車椅子を先頭車両に見立て、その後ろに連なる客車部分を構成します。並べ方を変えると車内のシートに変わります。小さい方の「ミニSL」(約55×22×27cm)は上部に持ち手があり、スチームダンサーがトランクのように持ち、動かすことで疾走感などさまざまな表現を生みます。
車窓フレーム
金属パイプで構成された「車窓フレーム」(約1.7×2.1m)は、ハンガーラックのような形状にキャスターが付いていて自在に動かせます。シンプルな構造が自由な見立てを可能にし、連ねれば列車が走るように見え、窓や壁、内外の境界を表し、ひっくり返すことで内と外の空間を瞬時に反転させることもできます。
踏切ポール
遮断機にもレールにも見立てられる長さ4mの棒は、物語の始まりと終わりに印象的に登場します。一本の棒が線を生み、時に境界を示し、時に道を開きます。
対象そのものを構造体として再現して説明するのではなく、抽象的なものに「動き」を与えることによって立ち上がる景色は、見える見えないに関係なく、想像力によって、一人一人違うものとなるのかもしれません。
世界観を伝える色と質感
舞台上には、歯車や回転する仕掛けなど、"動きそうなもの"が多く配置されています。金属の光沢を生かしながらも、表面にあえて錆びやくすみを加え、長い時間を経た深みを表現。蒸気機関車が最先端の象徴だった時代の憧れと懐かしさが交錯します。
メカニカルな重厚さとシンプルな造形を組み合わせ、現代の登場人物たちの存在を重ね合わせることで、未来へと続く時間の広がりを感じさせます。照明もその象徴で、レトロな意匠の灯りに現代の光がともり、時代を越える空気を漂わせます。
また、通常は袖中に隠される小道具も、舞台上にそのまま存在します。使われない小道具たちが舞台にあり続けても背景として調和するよう、渋めのゴールドで統一されています。
本作の美術の見どころ
美術を手がけた大島広子は、今回の見どころを「美術と身体性の融合」だと語ります。「さまざまに見立てられた美術が、キャストの身体の一部のように連動し、空間そのものを変化させていきます。そうした美術と身体の一体感こそがこの作品の魅力です。衣装のパーツにも美術的要素が組み込まれることで、複数の要素が呼応して世界観を生み出しています。」
こうした創作の根底にあるのが、制作初期から共有されていた「アクセシビリティ」の視点です。後から付け足すのではなく、クリエイションとして何ができるのかを探り続ける環境があったことで、美術・音楽・衣装・身体表現の要素がゆるやかにつながり、時間をかけて一つの作品へと結実していきました。
「劇場の中で、つくる人も観る人も同じ列車に乗っているような"いっしょにいる"感じが安心感につながっていると思います。同じものを見ていても、見え方はそれぞれ違っていい。その違いを楽しむための余白が、この舞台にはたくさんあります。」
同じ景色を、異なる視点で。その重なりの中に、『TRAIN TRAIN TRAIN』が目指す"共に旅をする美術"が息づいています。