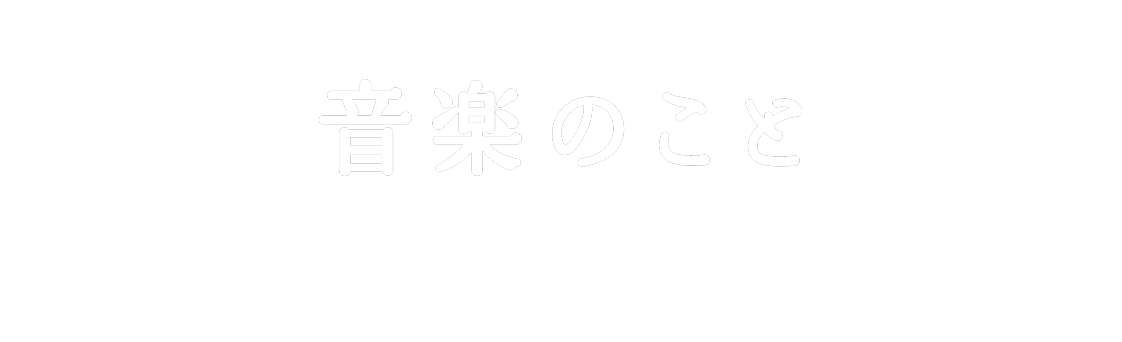音楽のこと
本作の音楽は、舞台上にいる楽隊によって生演奏されます。聞こえる人、聞こえない人が共にいるなか、「音がなければ音楽でないのか」「音楽とはなにか」という問いに向き合い、その原点から始まった創作について紹介します。
目次
見えない音を可視化する
蓮沼しゅうた執太、イトケン、三浦千明、宮坂遼太郎の4人で構成される楽隊は、聞こえる人に限定されない音楽を探りながら、美術チームとも対話を重ねてきました。公演中、楽隊たちは舞台の中央奥に位置し、生演奏を行います。
丸い楽器などいくつかあえて空間に散りばめるように吊るし、手や体の動きがより大きく見えるよう工夫されています。楽器を構える、息を吹く、バチで叩くといった"演奏する身体"から生まれる動きそのものを観客に届けます。
"聞こえる美術"としての音
聞こえない方も楽しめる音楽に挑戦する一方で、視覚に障害がある方は、音でこの舞台を楽しみます。音だけで何が舞台上で起きているのかを想像できるように意識しながら、音づくりが行われました。
たとえば、複数回登場する遮断機のシーンではトライアングル、サスペンション、トイピアノなどを使い、月のシーンではカウベル、ブロックなどを使って、同じ音のモチーフをベースに変奏して音が奏でられます。この音が聞こえたらこの場面、というように、音が"見えない美術セット"の役割を担い、「SLムジカ」の旅する情景を音で楽しめるようになっています。
また、録音された効果音を流すだけでなく、舞台上で実際に音を生成することで、聞こえない方にも見えない方にも届く工夫がされています。
本作における音づくり
汽笛から生まれた音のモチーフ
音づくりにあたって、汽笛の音を解析し、そこから得られた「ファ」「ソ」「ド」「レ」の音をモチーフに、この作品の基調となる音が決定されました。音域が近い音の組み合わせは、わずかな音のぶつかりや濁りを生み、少しのひっかかりをもたらします。
実際の汽笛の音や、踏切音にもあるその隣接音のぶつかりは、違和感により注意を促す働きをもちます。本作では、「エレクトレトロ駅」や「人形さん」の登場シーン、「泉」のシーンなど、多くの楽曲や効果音にその"気づき"の手がかりを仕込み、音楽に統一性をもたせるとともに、きれいに通り過ぎない音によって、旅の情景を記憶に刻みます。
さらに、汽笛を和合由依が奏でるユーフォニアムで表現するシーンも繰り返し登場します。この汽笛が発する「ミ・ソ・ド」は、希望を表す音列で、出発の瞬間や、命が再び息づくような場面で象徴的に響き、煙突のようなユーフォニアムの造形と、聴覚的な響きが希望のリズムとして重なり合います。

丸い楽器で表現する"月"
本作の象徴であり、何度も登場する"月"の音楽は、複数のシンバルや太鼓、スチールパン、ハピドラム、ドラなど丸の形をもつ楽器群を使って届けられます。形から発想するという新しい音づくりの挑戦により、視覚的にも月への連想が広がるよう工夫されています。
羽ペンを使った"描く音楽"
詩人・レンと、作曲家・ペンの共通モチーフとして作品の中に頻繁に登場する羽ペン。
羽ペンで楽譜を描くシーンでは、楽隊が実際にカリカリと描く音を奏でます。ベンの羽ペンが紙の楽譜を飛び出し、あちこちに描くのに合わせて、ぺンや紙、板など素材を変えながら、線の太さ・圧・スピードを音に変換していきます。描く動作がそのまま"描く音楽"となり、空間に広がります。
声のアプローチについて
坂本美雨が演じる女神・メモリーは、息と歌の間にあるような響きでしばしば空間を包みます。
声を身体から始まる表現として日頃から捉えている坂本は、"女神"として、今回は「息」が生命そのものであることを意識し、ときに人形に息を吹き込むように声で表現をします。
たとえば泉のシーンでは、湿り気のある空気に包まれるような発声を意識し、呼吸量や響きを細かく調整しながら、声で空間そのものを包むアプローチをしています。ダンサーや楽隊など"自分以外の表現者"によって、息が声や歌となって踊り出す瞬間も大切にしています。楽隊は坂本が発する声を"溶け合うもの"として受け取り、物語の展開に合わせて音を変化させ、空間いっぱいに響かせていきます。
稽古を重ねるなかで、動き・歌・演奏・感情のつながりが少しずつ立ち上がり、声と音が自然と寄り添い合う関係を育てていきました。
音と声、歌と言葉。そのあいだにある小さな余白が、この作品ではとても大切に扱われ、女神・メモリーの息づかいや楽隊の一音一音が、公演ごとに少しずつ異なる表情を見せるはずです。
サイン・ミュージック
への応答
本公演の終盤には、ろう者の音楽表現である「サイン・ミュージック(Signed Music)」が登場します。楽隊4人は、本作を通してこの表現に出会い、サイン・ミュージックの監修を務めるSasa-Marieのワークショップなどを通じて、「音がなければ音楽でないのか」「音楽とはなにか」という問いに改めて向き合ってきました。
まず、音を空気の振動として捉え、耳で音楽を聴いているという前提を疑うことから創作が始まりました。楽隊を率いる蓮沼しゅうた執太は、「絵画や写真を見て音楽的だと感じることがあります。もしかすると、"音楽"として認識するのは耳ではないのかもしれません」と語ります。
そうした思考の先に、サイン・ミュージックがあるのではないか。そしてそれは、2幕の最後に聴覚を失った作曲家・ベンが完成させる交響曲――"ムジカ"への挑戦にも重なっていきます。単に無音のサイン・ミュージックに"音をつける"のではないアプローチを探りました。相手の動きを見すぎたり、音を聴きすぎたりすれば、ただ"合わせる"ことになってしまうからです。そうではなく、一人ひとりが自分の表現をどう存在させていくか。互いの呼吸を感じつつも"対等に奏で合う"という関係を探りながら応答していきます。
耳だけで聴くのではない、身体と心で受け止める新しい音楽のかたち。その探求の過程こそがもっとも刺激的な"共奏"として、ベンの交響曲の中に響きます。
本作の音楽の見どころ(聞きどころ)
楽隊たちは、仲間とともにこれまでにない音楽を模索してきました。
「音楽が主役ではないにもかかわらず、舞台上ではほとんど途切れることなく音が生まれ続けています。それほどまでに、音と身体と物語が密接に結びついている舞台なので、楽しみ方は十人十色。その多層性こそを味わってほしい」と、楽隊たちは口を揃えます。
「音楽とはなにか?」という根源的な問いへと向き合い、目で聴き、耳で見ることができる舞台で、楽隊たちが生み出す音楽を感じてみてください。
♬〜本作のライブ音源を聴く(8分38秒)